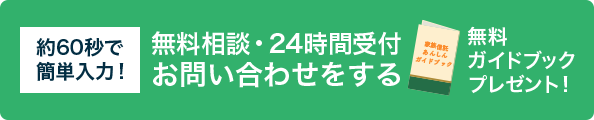相続税対策として、よく知られているのが生前贈与。
預貯金や株だけではなく不動産も生前贈与することができますが、不動産の生前贈与には注意するべき点もあります。
一方で不動産生前贈与ならではのメリットもあります。
生前贈与をして得なケース・損なケースを知っていきましょう。
不動産を生前贈与するメリット
不動産の生前贈与を行うと、不動産を継承させることができたり、節税効果があったりなど、様々なメリットがあります。
ちなみに、生前贈与した不動産は「特別受益」となり、相続時に法定相続分が変更になる可能性があることは知っておきましょう。
譲る相手を選択できる
不動産を生前贈与するメリットは、まず譲る相手を選択できること。
遺言でも継承させる人の指定ができますが、遺言がないと法定相続分に則って相続をするので、被相続人にはどの財産が誰に相続されるかわかりません。
特定の人物に受け継がせたい不動産がある場合には、生前贈与をすることを一考する事もおすすめです。
また、不動産を孫に生前贈与することで、通常の相続よりも20%余分に相続税がかかりますが、相続を1回パスできる分、トータルで見れば節税効果は高くなることも多く見受けられます。
節税ができる
不動産の生前贈与は、節税にも役立ちます。
生前贈与をした時には贈与税がかかりますが、この贈与税の計算に用いる評価額は生前贈与時のものなので、相続時に値上がりした場合には節税となります。
逆に相続時に値下がりした場合は損になってしまいますが、周辺の都市開発が決まっているなど、値上がりが見込める場合は生前贈与を検討した方が良いでしょう。
また、不動産から収益を得ている場合、贈与した不動産から発生する収益は、当然ながら贈与を受けた人の収入となります。
相続の場合、不動産収益による預貯金にも相続税が課されるので、生前贈与によって遺産総額を減らすことが可能。こちらの面でも、節税に繋がるのです。
短期間に贈与が可能
生前贈与だと、相続の場合に比べて短期間で不動産を継承できます。
相続の場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行なう必要があったり、名義変更のために多くの書類を用意しなければならなくなったります。
不動産の生前贈与は、贈与税の問題はありますが、時間と手間の節約になります。
不動産を生前贈与するデメリット・注意点
不動産の生前贈与には、デメリットも存在します。
安易に生前贈与を行うと損をしてしまうこともあるため、実行に移す前にしっかり考えておきましょう。
生前贈与の注意点
まず、亡くなる前に不動産を贈与しても、そもそも生前贈与と認められない場合もあります。
死亡から遡って3年以内の贈与は、相続税の計算においては、受贈者の財産ではなく、被相続人の相続財産として扱われますので、相続税の対象です。
自分が死亡する時期を予測できる人はいませんので、生前贈与が意味をなさなくなるケースもあることは知っておきましょう。
また、生前贈与は節税の方法として使えますが、税率自体は贈与税より相続税の方が低いです。
そのため、収益用不動産ではなく、値上がりも見込めないという不動産では節税効果はあまりありません。
さらに、不動産に限らず生前贈与した財産は遺留分減殺請求の対象になる場合があります。
そのため、配偶者や子供といった法定相続人が遺留分を主張すると、受贈者が不動産を手放さなければならなくなる可能性もあるのです。
不動産取得税や登録免許税がかかる
不動産の生前贈与を行うと、通常の不動産の授受と同じく不動産取得税・登録免許税がかかります。
生前贈与時にかかる不動産取得税・登録免許税の税率は、以下の通り。
不動産取得税:固定資産評価額の3%(土地・住宅)または4%(住宅以外の建物)
なお、宅地の場合、固定資産評価額の1/2を課税価格とする特例措置があります。
登録免許税:固定資産評価額の2%
一方、相続の場合は不動産取得税が発生せず、登録免許税の税率は0.4%になります。
不動産の生前贈与を行うと、手続きにかかる税金が高くなることは知っておきましょう。
維持費は受贈者が負担する
不動産の生前贈与を受けると、当然それ以降の不動産の持ち主は受贈者となります。
受贈者はその不動産を賃貸に出したり売却したりして収益を得られる反面、維持費などの負担もしていかなければいけません。
また、不動産から得た所得は給与や事業収入とは別に確定申告をする必要があるため、その手間や税理士に依頼する費用も発生することになります。
不動産の生前贈与で利用できる制度
不動産の生前贈与をするときは、税金の発生を後回しにしたり、贈与の非課税枠を利用して節税したりすることが可能です。
不動産の生前贈与で利用できる制度について、解説していきます。
一時的に税金が発生しない「相続時精算課税制度」
相続時精算課税制度は、子供や孫に生前贈与をする場合にのみ使える制度です。
これを利用すると、最大2,500万円までの贈与に贈与税がかかりません。
また、2,500万円を超える部分についても贈与税の税率が一律20%となります。
ただし、2,500万円以下の不動産なら無税で贈与できるのかというとそうではなく、遺産の相続時には「生前贈与された財産」と「相続財産」を合わせた金額に相続税がかかります。
実質的には、税金の発生を先送りにできるという制度です。
相続時の財産が相続税の基礎控除以下になる場合や、値上がりが見込める不動産、収益不動産の贈与をする場合などに節税効果があります。
年間110万円以下なら非課税の「暦年贈与」
財産の贈与を行うとき、誰に対してでも年間110万円以下であれば贈与税がかかりません。
これを利用して、「暦年贈与」といって少しずつ不動産を贈与することも可能です。
土地や建物を、一度に贈与する分の評価額が110万円以下になるように小さく区切り、複数年かけて贈与していくという方法です。
先にお伝えしたように、年間110万円以下であれば相手を問わず非課税で、税務署への申告も不要なため、子供や孫など近しい親族以外に不動産を贈与したい場合にも使えます。
しかし、毎年同じ金額を贈与していると、一年目に合計金額を分割で受け取る権利を贈与(定期贈与)したとみなされ、合計金額に贈与税が発生する可能性があるので注意が必要です。
不動産を生前贈与する手続き方法
それでは、実際に不動産を生前贈与する場合の手続き方法を解説していきます。
必要書類を用意する
不動産の生前贈与に必要な書類は、以下の通りです。
・不動産贈与契約書
・不動産の登記済権利証(登記識別情報通知)
・贈与者の印鑑証明書(3か月以内に取得)
・受贈者の住民票
・固定資産税評価証明書
・不動産の登記簿謄本
上記のうち、「不動産贈与契約書」は法務局での手続きに必ず必要な書類ではありません。不動産の贈与は、口約束のみでも法的な拘束力を持ちます。
しかし、後のトラブル防止のためにも「誰が、誰に、どの不動産を贈与するか」を記載した贈与契約書を作成しておくべきです。
申請書を作成し、法務局へ提出する
必要な書類が揃ったら、法務局で不動産の名義変更の手続きを行います。
不動産の名義変更を行う申請書は、「登記申請書」です。
申請書と書類一式を提出し、登録免許税を納付することで、不動産の贈与が完了となります。
申請内容に間違いがなければ、受贈者に「登記識別情報通知」が送られてきます。
納付時期・申告期限に注意
不動産の生前贈与をしたら、翌年の2月1日~3月15日の間に受贈者が贈与税の申告手続きを行います。
この手続きを行うのは、法務局ではなく受贈者の住所地を管轄する税務署です。
ただし、不動産の評価額が110万円以下の場合は、贈与税がかからないため申告も必要ありません。
贈与税の納付期限も、申告期限と同じく贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日です。
不動産の生前贈与にかかる税金
最後に、不動産の生前贈与を行うと発生する税金について解説します。
登録免許税
生前贈与に限らず、不動産の名義変更を行うと「登録免許税」がかかります。
この登録免許税は、贈与者・受贈者どちらが納付しても問題ありません。登録免許税の金額は、「固定資産税評価額の2%」です。
ちなみに先にも触れましたが、相続によって不動産を取得した場合の登録免許税は「固定資産税評価額の0.4%」です。
不動産取得税
不動産の生前贈与には、「不動産取得税」という税金もかかります。
不動産取得税は不動産の名義変更をして6ヶ月くらいで受贈者に通知が届き、受贈者が納付します。
不動産取得税の金額は、「固定資産税評価額の3%(住宅以外の建物は4%)」です。
なお、宅地の場合、固定資産評価額の1/2を課税価格とする特例措置があります。
ちなみに相続で不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。
贈与税
贈与税は年間110万円を超える財産を贈与した場合に発生し、受贈者が納付します。
贈与額が大きくなるほど税率も高くなる累進課税制度を採用していて、税率は10~55%です。
贈与税は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」で税率が異なり、親や祖父母が子・孫に贈与する場合の特例贈与財産の方が税率は低くなっています。
まとめ
不動産を生前贈与すると、不動産の値上がりや不動産収益によって遺産総額が大きくなるのを防ぎ、節税できるというメリットがあります。
また、法定相続人以外に不動産を譲ったり、譲る人を指定できたりするのもメリットです。
ただし、贈与税は相続税より税率が高いため、得にはならないケースもあります。
生前贈与のメリット・デメリットを把握して、相続時に損をしないように調整していきましょう。